生後2ヶ月からワクチン接種が始まります。赤ちゃんのワクチン接種ってどうやって受けるんだろう。スケジュールは?まとめて受けるのかな?と疑問に思うと思います。私が子供を連れた時の実際の体験も交えて解説します。参考になれば幸いです。
1.生後2か月からの「命を守るワクチン」

絶対に外せない4大ワクチン
| ワクチン | 最大のリスク | 接種期限 | 命を救う効果 |
|---|---|---|---|
| ロタウイルス | 重症脱水症 | 生後14週6日 | 入院リスク80%減 |
| ヒブ | 細菌性髄膜炎 | 5歳未満 | 発症率99%減 |
| 肺炎球菌 | 敗血症 | 5歳未満 | 重症化防止90% |
| B型肝炎 | 慢性肝炎 | 1歳未満 | 肝癌予防効果 |
ワクチンの種類と特徴
| 分類 | 種類 | 主な特徴 | 代表ワクチン例 | 接種間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 不活化ワクチン | 細菌/ウイルス成分 | ・死んだ病原体を使用 ・複数回接種が必要 ・接種間隔の制限なし | ヒブ、肺炎球菌、四種混合、B型肝炎 | 3~8週間隔 |
| 生ワクチン | 弱毒化病原体 | ・弱毒化した生きた病原体 ・接種後4週間は他の生ワクチンと間隔 | ロタウイルス、BCG | 4週間以上 |
2.最強スケジュールの組み方

①生後2か月~1歳の完全ロードマップ
2024年度に受けた実際のスケジュールは下記の通りです。
| 月齢 | 推奨ワクチン | 接種回数 | 同時接種例 |
|---|---|---|---|
| 生後2か月 | ロタウイルス、5種混合、肺炎球菌、B型肝炎 | 初回 | 4種同時接種 |
| 生後3か月 | ロタウイルス、5種混合、肺炎球菌、B型肝炎 | 2回目 | 4種同時接種 |
| 生後4か月 | ロタウイルス、5種混合、肺炎球菌 | 3回目 | 3種同時接種 |
| 生後5か月 | BCG | 単独/他ワクチンと組み合わせ | 地域により集団接種 |
| 生後8か月 | B型肝炎、(ロタウイルス) | ロタは追加の場合 | 2種同時接種 |
1回の受診で4本一気に注射します。小児科は患者さんが非常に多いです。予防接種の予約方法を余裕をもって1か月前に確認しておくと安心です。
27日以上の間隔があればよいので、予診票に「1か月以内に予防接種を受けましたか」とありますが、問題ありません。
インフルエンザワクチンも受けたい場合は、受けてもよいか医師に確認しましょう。
②接種前の必須チェックリスト
1. 体調管理のポイント
- 検温:接種当日の朝に37.5℃未満か確認
- 授乳タイミング:接種30分前までに済ませる(嘔吐時の副反応判別困難を防ぐ)
- 服装選び:接種部位を露出しやすく
腕まくりするので、肌着は半袖&着脱しやすい上着がいいです。
2. 持参物チェック
| 必須アイテム | 目的 |
|---|---|
| 母子手帳 | 接種記録の即時記載 |
| 予診票 | 事前に記入済みが理想 |
| 体温記録表 | 過去1週間の体調変化を提示 |
| お気に入りおもちゃ | 接種時の気分転換用 |
初めての来院の場合は、初診として住所など記入することが多いので、両手が自由になるように、ベビーカーや抱っこ紐を準備しておきましょう。
③接種当日のNG行動
- × 接種直前に授乳:嘔吐リスク上昇
- × 予防接種後に初めての離乳食:アレルギー反応と副反応の区別困難
3.読者が一番知りたかった「本当のこと」
「任意接種」は受けるべき?
→B型肝炎(2016年)やロタ(2020年)のように、数年後には定期接種化される可能性大。経済的に可能なら「受けておく」が専門家の見解。特に保育園入所予定なら、任意のインフルエンザワクチンも検討を。
ワクチンギャップ解消の現状
日本でもようやく「生後2か月からの同時接種」が標準化。世界基準に追いつく形で、15種類以上のワクチンが効率的に接種可能になりました。
4種混合と5種混合ワクチンの違い
2024年からの新しい定期接種で、本来別接種だったヒブ3回分の接種回数が減らせるのがメリット。
| 項目 | 4種混合(DPT-IPV) | 5種混合(DPT-IPV-Hib) |
|---|---|---|
| 予防疾患 | ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ | 4種混合+Hib感染症 |
| 抗原成分 | 4種類 | 5種類 |
| 定期接種化 | 2012年~ | 2024年4月~ |
夫婦で小児科を訪れても大丈夫?
大丈夫です。育児の疲れもありママの体調が思わしくない時もあります。3組に1組くらいご夫婦で来ていらっしゃいました。低月齢ほどその傾向があります。私も夫を連れて行きました。
4.絶対に守りたい3つのルール
- ロタ期限:生後14週6日は絶対厳守
- BCGタイミング:5~8か月の間に確実に
- 5種混合:生後3か月開始が百日咳予防の鍵
5.おわりに
生後8か月のワクチンが終われば、1歳になるまではひと段落です。毎月毎月病院に行くのは大変ですが、赤ちゃんが感染症にかからないように、またかかっても重症化しないようにするために必要なことです。近くの小児科を訪れる機会、相談する機会でもあります。赤ちゃんのためにも忘れずに受診しましょう。
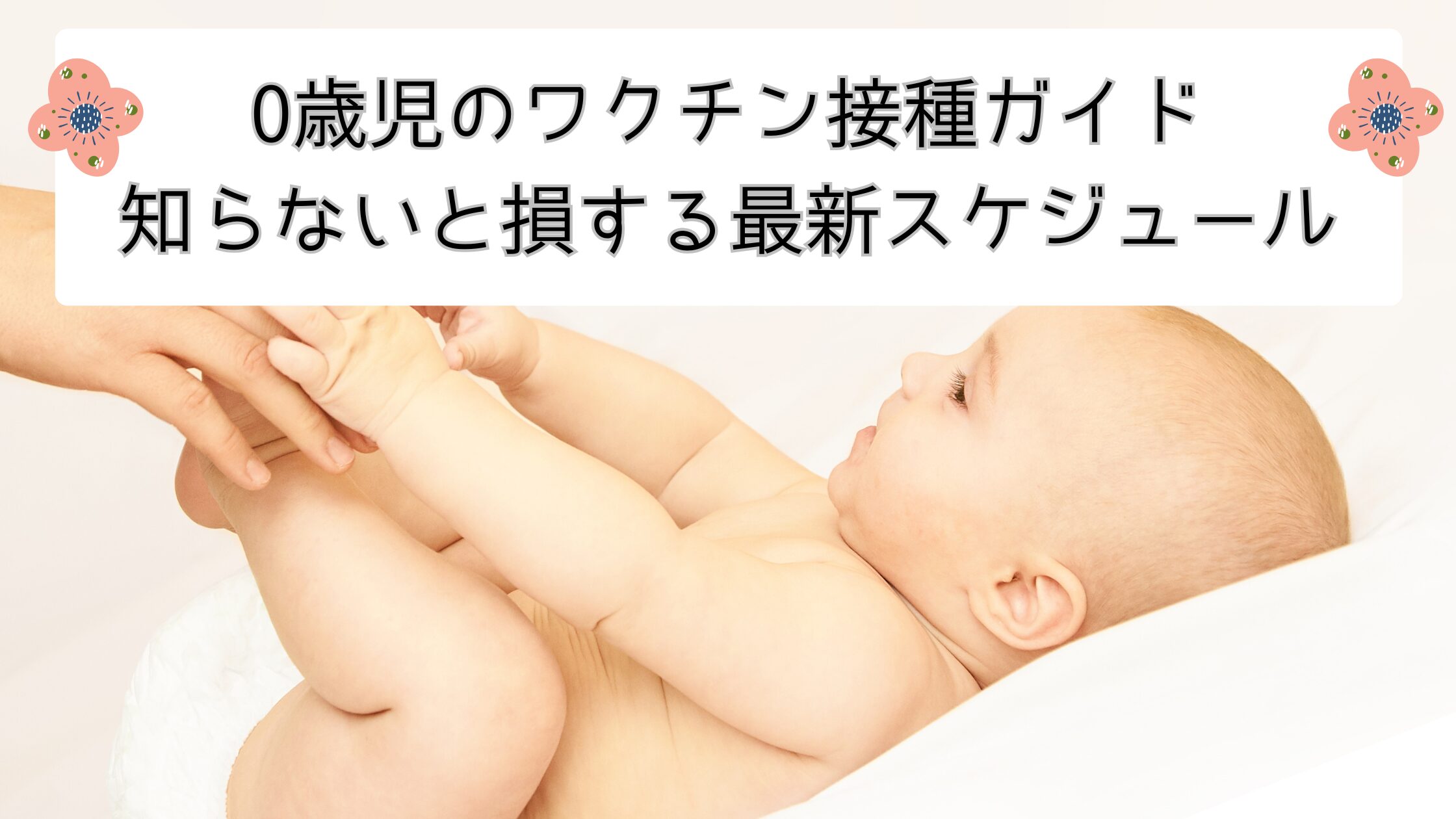


コメント